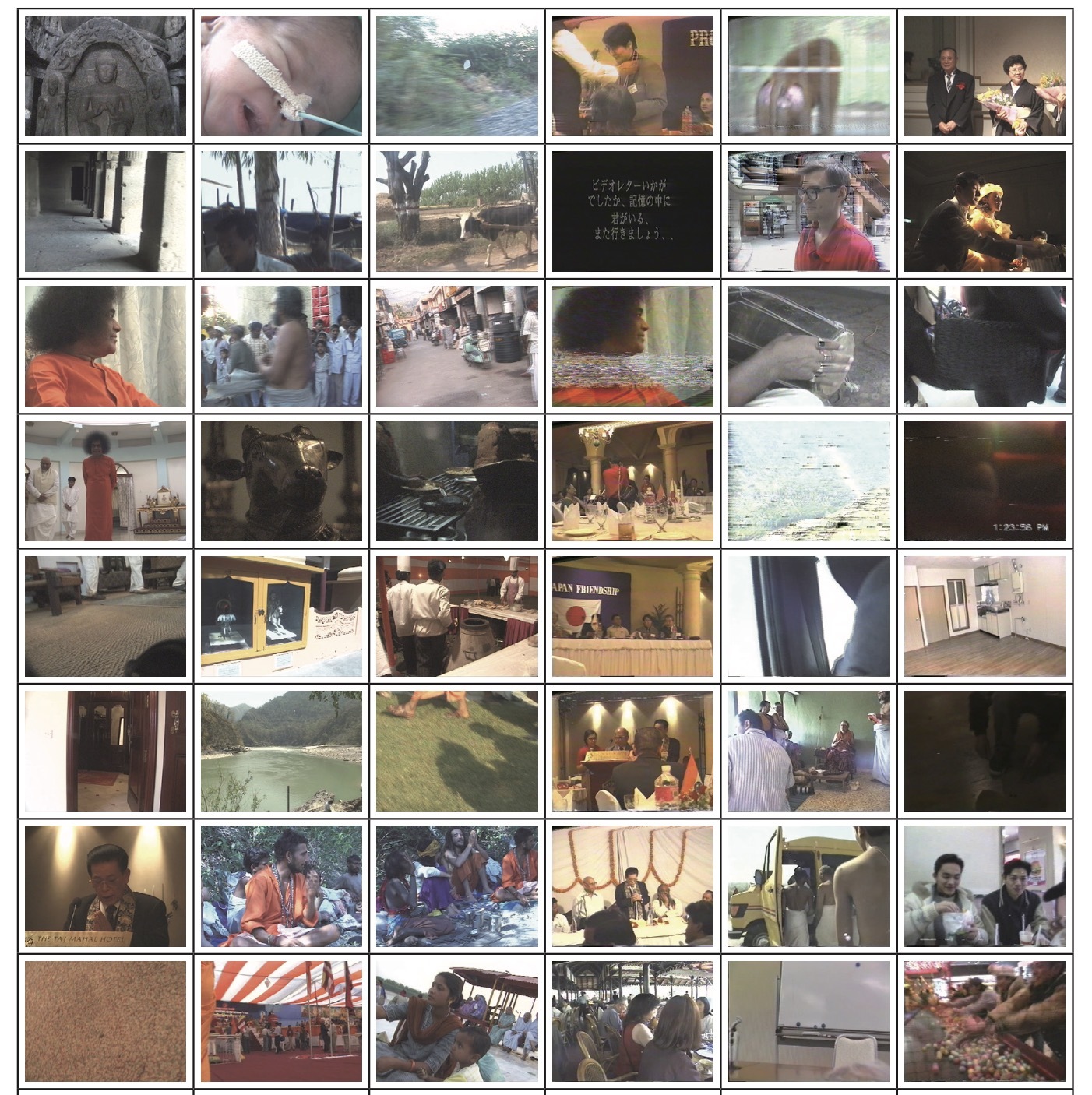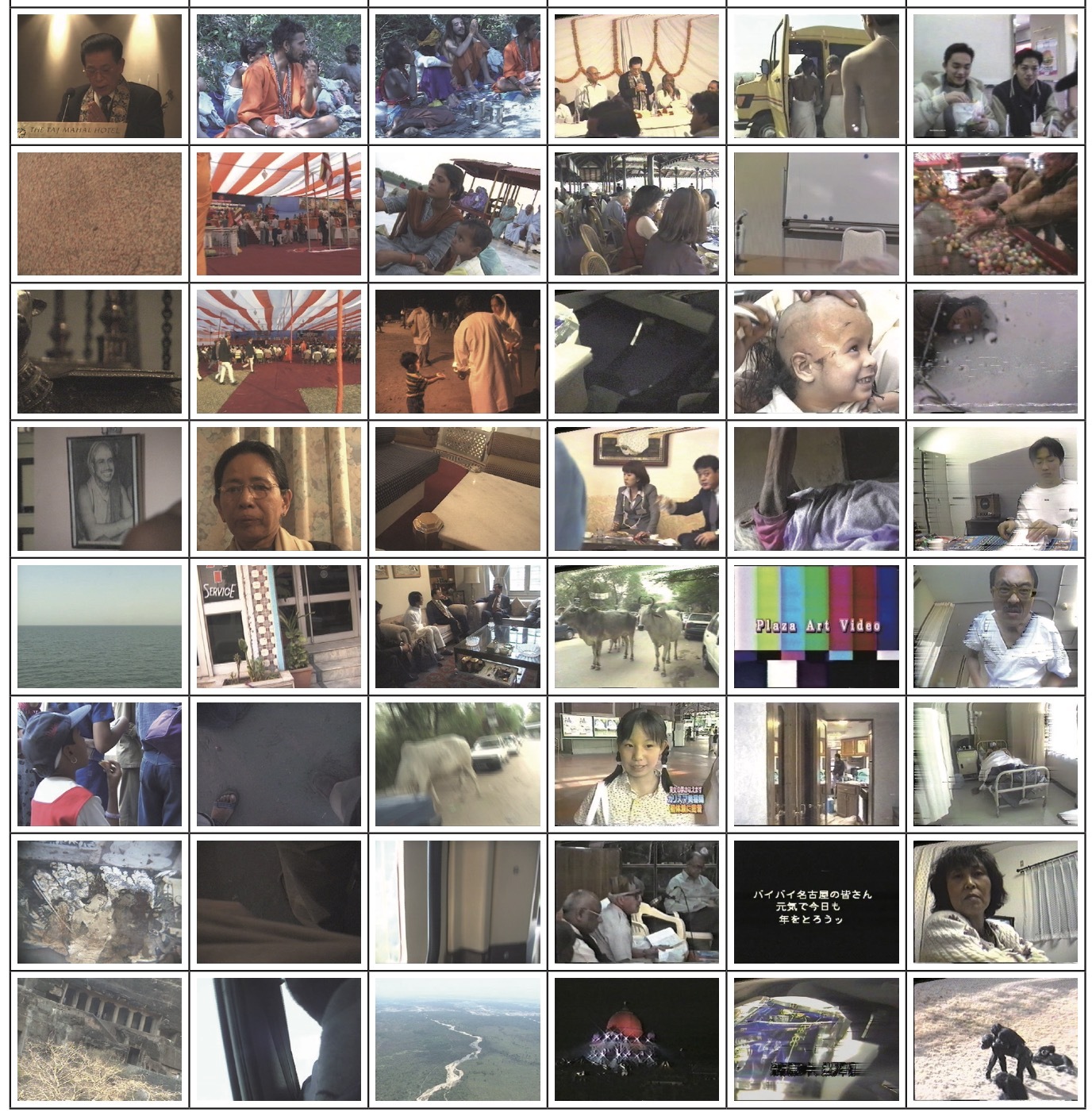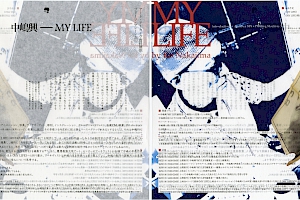1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化
本事業は、戦後から現代にいたる日本のメディア芸術の諸活動を、「インターメディア」という枠組みにおいてとらえ直し、芸術史・映像史という縦軸と、同時代の様々な芸術諸活動という横軸との交差点に位置するビデオアート関連資料群が包含するパフォーマンスおよび展覧会記録に着目し、それらのデジタル化・レコード化を通じ、日本のメディア芸術史をよりよく精査可能にするための基盤構築を目指す。
- お問い合わせ
久保仁志
pj.ca.oiek.c-tra@sevihcra
お知らせ/活動
イベント
【VICデータベース第2版】
上記はVICデータベースの第2版である。
デジタル化されたビデオテープの映像はすべてサムネイルが閲覧可能となっており、一部には内容既述や解説なども含まれている。
本事業の背景と必要性:ビデオ記録によって一過性の形体を有する作品(出来事)を掬い上げること/ビデオアートからメディア芸術史を構築すること
およそ1970年以降の芸術作品は、古典的な絵画や彫刻などの形体とは異なる、再現困難な一過性の形体(パフォーマンス/インスタレーション等)において実現される類の作品が多く、そのドキュメントや周辺資料によってしか作品へアプローチできないという条件がある。また、この時期は新旧のテクノロジーを連結させ、諸ジャンルの枠組みを横断させたタイプの作品が多い。それらのドキュメントとして主に流通していたのは写真による静止画だが、この時期にはビデオによる動画記録も多く残されており、時間性を孕んだ一過性の形体を有する作品の記録として、その重要性は計り知れない。こうした動画記録はビデオアートに与するものが多くある。この時期に培われたビデオアートでは、実験映画史と連続した問題を孕む作品群、複数の芸術ジャンルを連結させる「インターメディア」な機構、一過性の形体を有する作品(出来事)の記録、新たなコミュニケーション技術の構築実験、既存のメディアテクノロジーへの批判的考察等が行われていた。つまりビデオアートという枠組みにおいて、メディア芸術の重要な諸事象と諸問題が展開されているのである。
翻って戦後、〈綜合文化協会〉〈世紀の会〉〈夜の会〉や〈実験工房〉等を経て、草月アートセンター、そして「クロス・トーク/インターメディア」や「70年大阪万博」にいたるまで「芸術の総合」が重要な問題の一つとされ、様々な形で展開されてきた。これらを端的には「インターメディア」問題とまとめることができる。それは固有の芸術領域の閉塞状態を突破したり、そのさらなる展開を模索するために異なる芸術領域をいかに相互に関連づけ触発しあうのかについての方法論の探求と、新たなテクノロジーへの批判的な吟味だと言い換えられる。1970年代以降も明示的ではない形ではあるが「インターメディア」問題は重要であり続け、arts-uni(アール・ジュニ)やARTEC(アーテック)など様々な形で展開され、1997年にICC(NTTインターコミュニケーション・センター)が設立され「インターコミュニケーション」という領域横断的なテーマが提示された。しかしどちらかと言えば、技術的な領域横断の問題へと一般化される傾向があったことは否めない。この探求の主戦場の一つとなったのはダンスや演劇や美術や音楽におけるパフォーマンス(以下諸領域にまたがりパフォーマンスと総称する)、そして展覧会である。これら1970年以降の「インターメディア」の状況を踏まえ、その歴史化を行うための資料体構築を目指した。
さらにKUACで行ってきた現在までの資料体構築の過程で、中嶋興とVICの資料体の中には多くのパフォーマンス/展覧会記録があり、両者の活動は日本に留まらず世界的にも重要だと認知され、国際的な関心を集めていることが分かっている。しかし、両者の資料体の中に含まれる写真やビデオテープの中には劣化が進んでいる資料が多くあり、早急のデジタル化を行う必要に迫られている。もし、数年以内にこれらのデジタル化を行わなければ、1970年以降のパフォーマンスおよび展覧会の重要な記録の一部が消失してしまう可能性があると言える。
また、一過性の形体を有する芸術作品の代表的な一例である「もの派」の国際的な研究動向の進展が示しているように、1960年代後半以降の日本の芸術活動に関する世界的な関心の増大に対し、日本におけるビデオアートの調査・研究によって多くの応答が可能であり、国際貢献度も高まる。本事業は、1970年以降のビデオアートの中心的な担い手である中嶋興とVICの関連資料群を通して、ビデオ記録によって一過性の形体を有する作品(出来事)を掬い上げること、ビデオアートからメディア芸術史を構築することを目的とする。具体的事業内容は中嶋興とVICのビデオテープのデジタル化・レコード化・サムネイル化およびリスト整備(ビデオテープ以外の物資料を含む)、および公開用のVICビデオ関連データベースの作成である。また、演劇のビデオ記録というモデルを通して単独的な出来事と記録の関係性について考えるイベントを行った。
● 令和6年度 メディア芸術アーカイブ推進支援事業 メディアアート分野「1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化II」について
本事業は、戦後から現代にいたる日本のメディア芸術の諸活動を、「インターメディア」という枠組みにおいてとらえ直し、芸術史・映像史という縦軸と、同時代の様々な芸術諸活動という横軸との交差点に位置するビデオアート関連資料群に着目し、それらのデジタル化・レコード化を通じ、日本のメディア芸術史をよりよく精査可能にするための基盤構築を目指した。
「インターメディア」問題とは、固有の芸術領域の閉塞状態を突破したり、そのさらなる展開を模索するために異なる芸術領域をいかに相互に関連づけ触発しあうのかについての方法論の探求と、新たなテクノロジーへの批判的な吟味だと言える。この探求の主戦場の一つとなったのはダンスや演劇や美術や音楽におけるパフォーマンス、そして展覧会である。
慶應義塾大学アート・センターが所管している「中嶋興」(1941–)および「VIC」(Video Information Center, 1972–)関連資料の中からパフォーマンスと展覧会の記録に着目し、ビデオテープと写真のデジタル化・レコード化・リスト化を行うことによって、1970年以降どのように「インターメディア」問題が模索されていたのかについて明らかにすることを目指した。そのため、中嶋とVICのビデオテープのデジタル化、レコード化、サムネイル化、およびリスト整備を行うとともに、公開用のVICビデオ関連データベースを作成した(2025年4月より公開予定)。
また、VICについて考えるためのイベントVIC x KUAC Chinematheque 3:状況劇場「唐版・犬狼都市」上映会―単独性と反復または記録について(2025年2月1日)を行った。本事業は令和2, 3, 4年度メディア芸術アーカイブ推進支援事業「中嶋興/VICを基軸としたビデオアート関連資料のデジタル化・レコード化 [I], II, III」 (以下「令和2, 3, 4年度事業」)および、 令和5年度メディア芸術アーカイブ推進支援事業「1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化」(以下「令和5年度事業」)を発展的に引き継ぐものである。
● 令和5年度 メディア芸術アーカイブ推進支援事業 メディアアート分野「1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化」について
本事業は、戦後から現代にいたる日本のメディア芸術の諸活動を、「インターメディア」という枠組みにおいてとらえ直し、芸術史・映像史という縦軸と、同時代の様々な芸術諸活動という横軸との交差点に位置するビデオアート関連資料群が包含するパフォーマンスおよび展覧会記録に着目し、それらのデジタル化・レコード化を通じ、日本のメディア芸術史をよりよく精査可能にするための基盤構築を目指す。
戦後、〈綜合文化協会〉〈世紀の会〉〈夜の会〉や〈実験工房〉等を経て、草月アートセンター、そして「クロス・トーク/インターメディア」や「70年大阪万博」にいたるまで「芸術の総合」が重要な問題の一つとされ、様々な形で展開されてきた。これらを端的には「インターメディア」問題とまとめることができる。それは固有の芸術領域の閉塞状態を突破したり、そのさらなる展開を模索するために異なる芸術領域をいかに相互に関連づけ触発しあうのかについての方法論の探求と、新たなテクノロジーへの批判的な吟味だと言い換えられる。しかし、およそ1970年代以降も「インターメディア」問題は重要であり続け、様々な形で展開されながらも、1997年にICC(NTTインターコミュニケーション・センター)が設立され「インターコミュニケーション」という領域横断的なテーマが登場するまで、直接的に焦点化されることがなかったと言えるだろう。この探求の主戦場の一つとなったのはダンスや演劇や美術や音楽におけるパフォーマンス(以下諸領域にまたがりパフォーマンスと総称する)、そして展覧会である。これら1970年代以降の「インターメディア」の状況を踏まえ、その歴史化を行うための資料体構築を目指す。
具体的には慶應義塾大学アート・センター(以下KUAC)が所管している「中嶋興」(1941—)関連資料と「VIC」(Video Information Center, 1972—)関連資料の中からパフォーマンスと展覧会の記録に着目し、ビデオテープと写真のデジタル化・レコード化・リスト化を行うことによって、およそ1970年代以降どのように「インターメディア」問題が模索されていたのかについて明らかにすることを目指す。
現在までの資料体構築の過程で、中嶋興とVICの資料体の中には多くのパフォーマンス/展覧会記録があり、両者の活動は日本に留まらず世界的にも重要だと認知され、国際的な関心を集めていることが分かっている。しかし、両者の資料体の中に含まれる写真やビデオテープの中にはカビの発生、ビネガーシンドローム化やバインダー化が進んでいる資料が多くあり、早急のデジタル化を行う必要に迫られている。もし、数年以内にこれらのデジタル化を行わなければ、1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会の重要な記録の一部が消失してしまう可能性があるため、ビデオテープに適切な処置を施すとともに、デジタル・データ化を行い、レコード化することが喫緊の課題であり、本事業においてこれらの解決を試みる。
また、中嶋興《MY LIFE》の最新版制作とそれに伴う勉強会を通じてこれら資料体=アーカイブを現代的な制作と接続し、1970年代以降の「インターメディア」問題についての研究を行う。さらに、昨年度事業において行った「マイ・ライフ勉強会II」(2024年1月31日|KUAC)のように、当室が大学内の研究所でもあることを活かし、VICと中嶋興の資料体を大学教育においても活用することを試みる。
- 1970年代以降のパフォーマンスおよび展覧会のビデオ記録のデジタル化・レコード化
- 中嶋興/VICを基軸としたビデオアート関連資料のデジタル化・レコード化Ⅰ・Ⅱ
- 都市のカルチュラル・ナラティヴ
- 「慶應義塾の建築」プロジェクト
- 1970年代アートの記録―Video Information Center を中心に
- #MuseumFromHome at KUAC
- ショーケース プロジェクト(SHOW-CASE project)
- 東京ビエンナーレ1970 研究プロジェクト
- ミーツ・アーティスト・イン・慶應
- ジェネティック・エンジン
- 舞踏:越境する身体
- アーツ・マネジメント教育の総合的・体系的確立とその方法論による人材養成事業